こんにちは、テンプルトンです。
働いて給与をもらうと、所得税,住民税が引かれます。それと同様に、株式投資で利益が出た場合も税金を払う必要があります。
今回は、株式投資にかかる税金について解説していきたいと思います。
株式投資の税金
前述した通り、株式投資で利益が出た場合には、納税の義務が生じます。
給与所得や不動産所得などとは分けて課税される、「分離課税方式」で計算されます。
株式投資の利益に対する税金は、いくら多くの利益が出た場合でも、消費税のように一律です。
所得税の場合、所得が一定金額を超えるたびに税率が高くなる「累進課税」ですので、所得が多ければ多いほど、税率も高くなり、より多くの税金を支払う必要があります。
株を買って、その買った金額より高く売ることができれば、売却益が得られます。
この売却益に対する税金は「20.315%(所得税15%+住民税5%復興特別所得税0.315%)」です。
逆に損が出てしまった場合には税金はかかりません。
株を買い、その株を決められた日付まで持っていると、配当金が得られることがあります。
これは、株を発行している会社が、その株を買った人(株主)に対するお礼としてもらえるお金です。
この配当金にも税金がかかり、税率は売却益と同じく「20.315%」です。
1月1日~12月31日の間に、利益が出た取引(配当金含む)と損が出た取引が存在する場合、
利益と損を相殺することが可能です。このことを「損益通算」といいます。
本来、この税金は自分で計算し、確定申告によって納税する必要がありますが、
証券会社の口座を作る際、「特定口座(源泉徴収あり)」を選び、この口座で取引することによって、面倒な税金の手続きを証券会社がかわりにやってくれます。
株式投資の場合、前述した通りいくら利益が出ても20.315%の税率ですので、仮に1億円の利益が出た場合、税金を支払った後でも8000万円弱のお金が残ることになります。
給与所得で1億円を得た場合、45%の税率が適応されるため、6500万円しか残りません。
(所得税の累進課税は4000万円以上で最高値45%の税率が適応)
NISAの活用で節税
テレビCM等で「NISA」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
NISAは日本語で「小額投資非課税制度」といい、一定額の投資枠から得られた利益に対して、税金がかからなくなる制度です。
NISA口座を使用し、株式投資の利益が出た場合、前述した20.315%の税率が0%となり、一切税金を支払う必要がありません。
NISAには一般NISAとつみたてNISAがありますので、それぞれ詳しく解説していきます。
(ジュニアNISAというNISAもありますが、2023年に制度が廃止する予定なため紹介しません。)
1.一般NISA
対象者:口座開設をする年の1月1日現在において満20歳以上の居住者等
※NISAとつみたてNISAはどちらか一方を選択して利用可能
口座開設可能数:1人1口座
非課税対象:株式・投資信託等への投資から得られる配当金・分配金や譲渡益
非課税投資上限額:年間120万円まで
非課税期間:5年間
上記が標準の一般NISAの概要になります。
年間120万円までの投資枠ですので、頻繁に買ったり売ったりする取引には向きません。
一般NISAの使い方として、「株や投資信託を買って値上がりするのを待つor配当金をもらう」というのが一般的です。
非課税期間が5年間ですので、株や投資信託を買って5年経過した時点で、「翌年の一般NISA枠に移行する(ロールオーバー)か、課税口座に移行するか、売却するか」のいずれかを行う必要があります。
一般NISA使用例:120万円で買った株が5年後200万円になったため売却し80万円の利益。本来であれば利益の80万円に20.315%の税金がかかるため、16万円強の税金を支払う必要があるが、一般NISAを使えば0円。
2.つみたてNISA
対象者:口座開設をする年の1月1日現在において満20歳以上の居住者等
※つみたてNISAとNISAはどちらか一方を選択して利用可能
口座開設可能数:1人1口座
非課税対象:一定の投資信託への投資から得られる分配金や譲渡益
非課税投資上限額:年間40万円まで
非課税期間:20年間
投資対象商品:長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託
上記がつみたてNISAの概要になります。
一般NISAとの違いは、投資枠が年間40万円までと少ない代わりに、非課税期間が20年と長いです。
つみたてNISAは名前にもある通り、一定金額をつみたてて投資することで非課税の恩恵を最大限に受けることができます。
一般NISAは株を購入する際も使用できましたが、つみたてNISAは金融庁が定める投資信託のみにしか使用できませんので、注意してください。
つみたてNISA使用例:毎年40万円ずつ積み立て、20年間で合計800万円の投資額。毎年約7%の複利運用の結果、800万円の投資額が1700万円になったため売却し、900万円の利益。本来であれば利益の900万円に20.315%の税金がかかるため、180万円強の税金を支払い必要があるが、NISAを使えば0円。
まとめ
いかがだったでしょうか。
給与所得等と株式投資の税率の違いやNISAについて、少しでも学びになれれば幸いです。
この税率の違いが、サラリーマンとして働いてもあまり裕福になれない原因でもあります。
給与所得だけでなく、投資を含めた色々な資産形成の仕方を考えていく必要があります。
NISAで章で、”ロールオーバー”という言葉を紹介しました。
これを詳しく解説するとかなり長くなってしまうため、今回は割愛しています。
ロールオーバーだけで1記事になってしまうので、また今後紹介していきます。


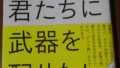
コメント